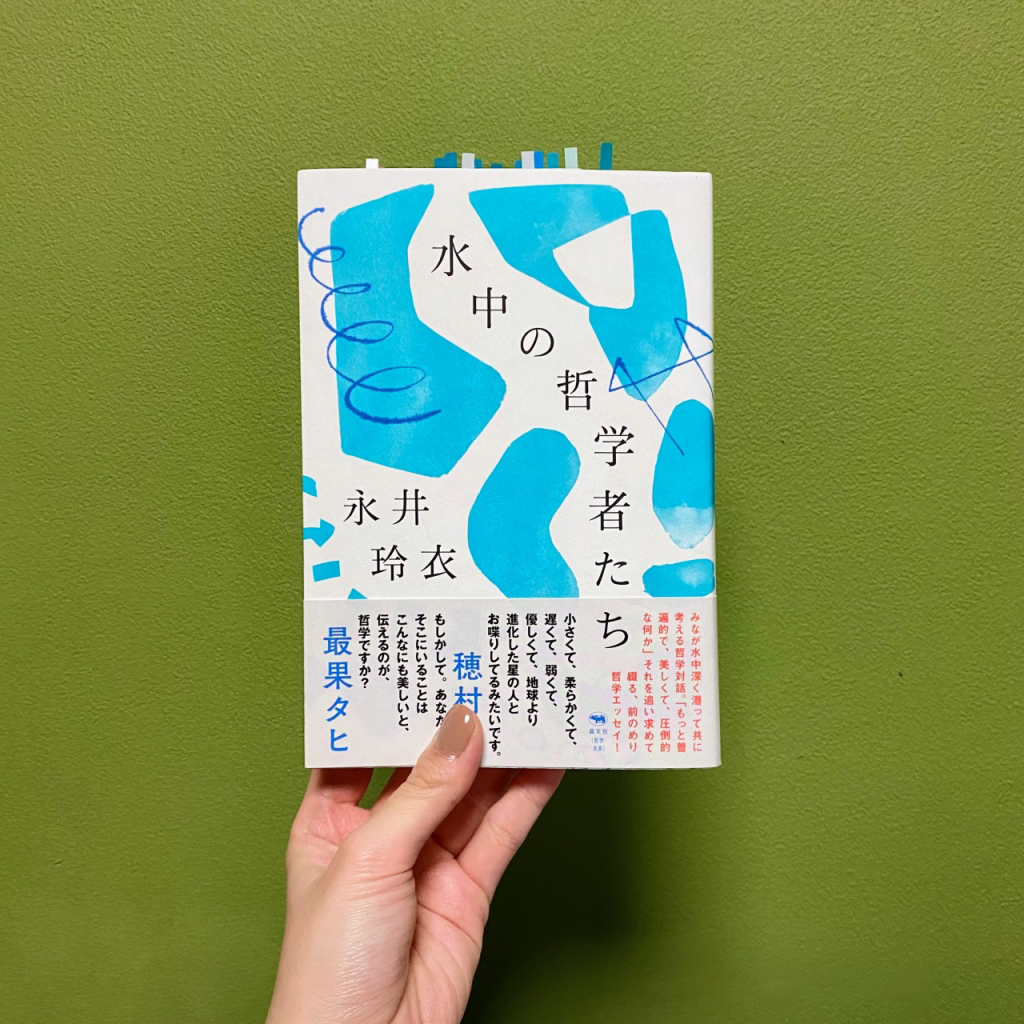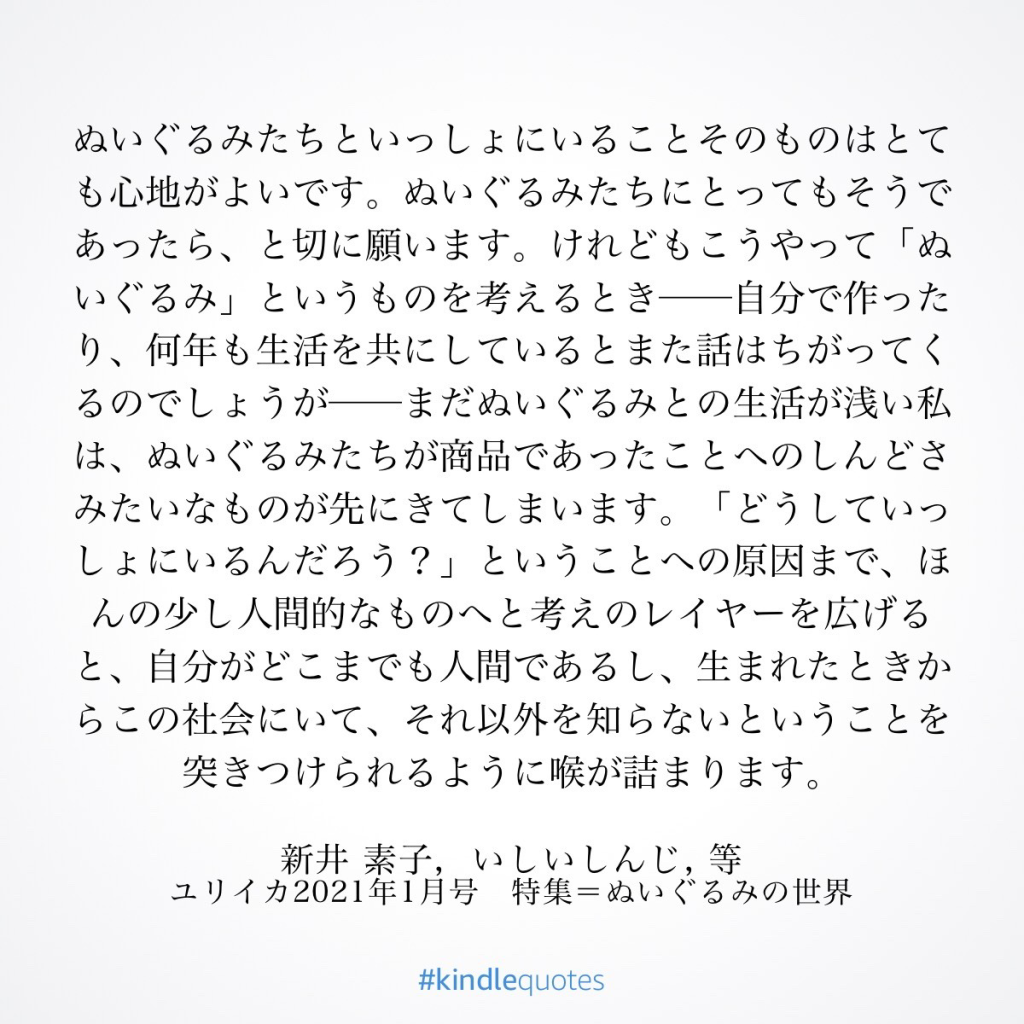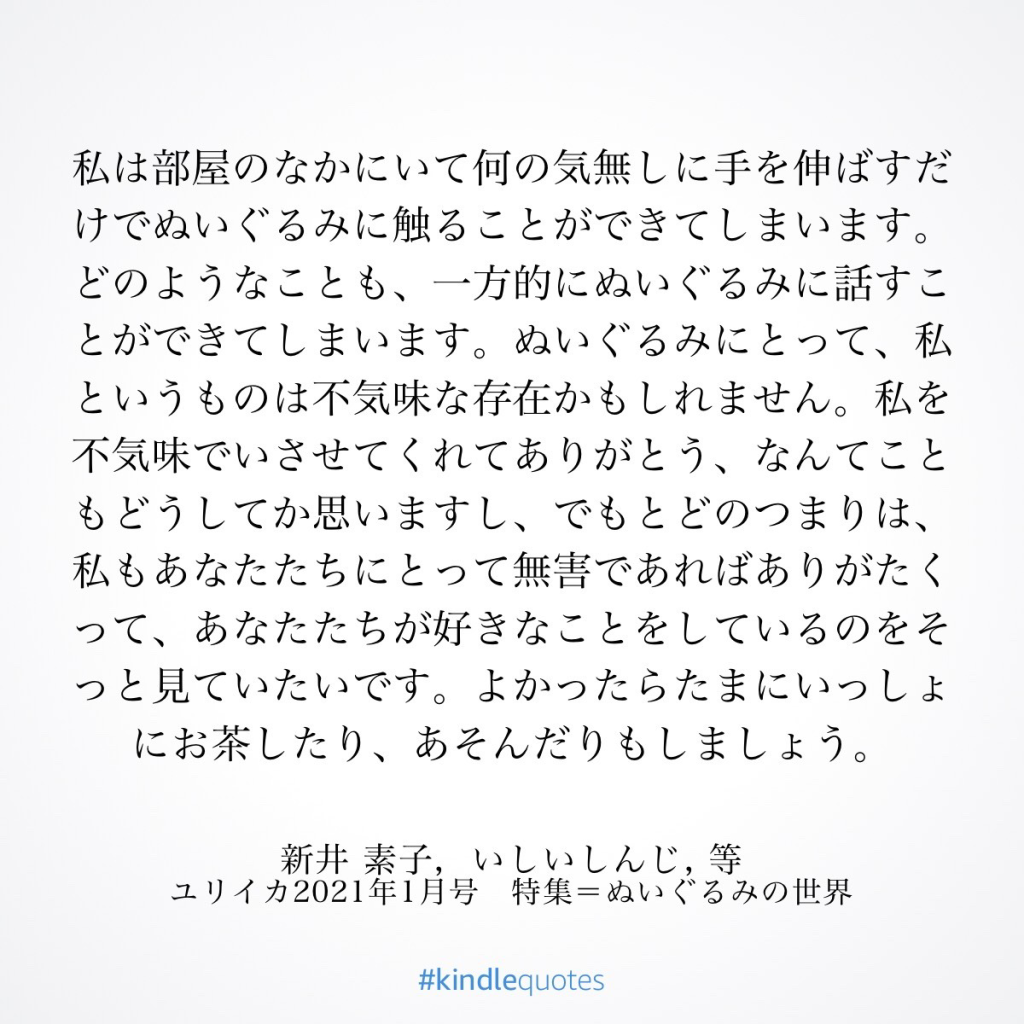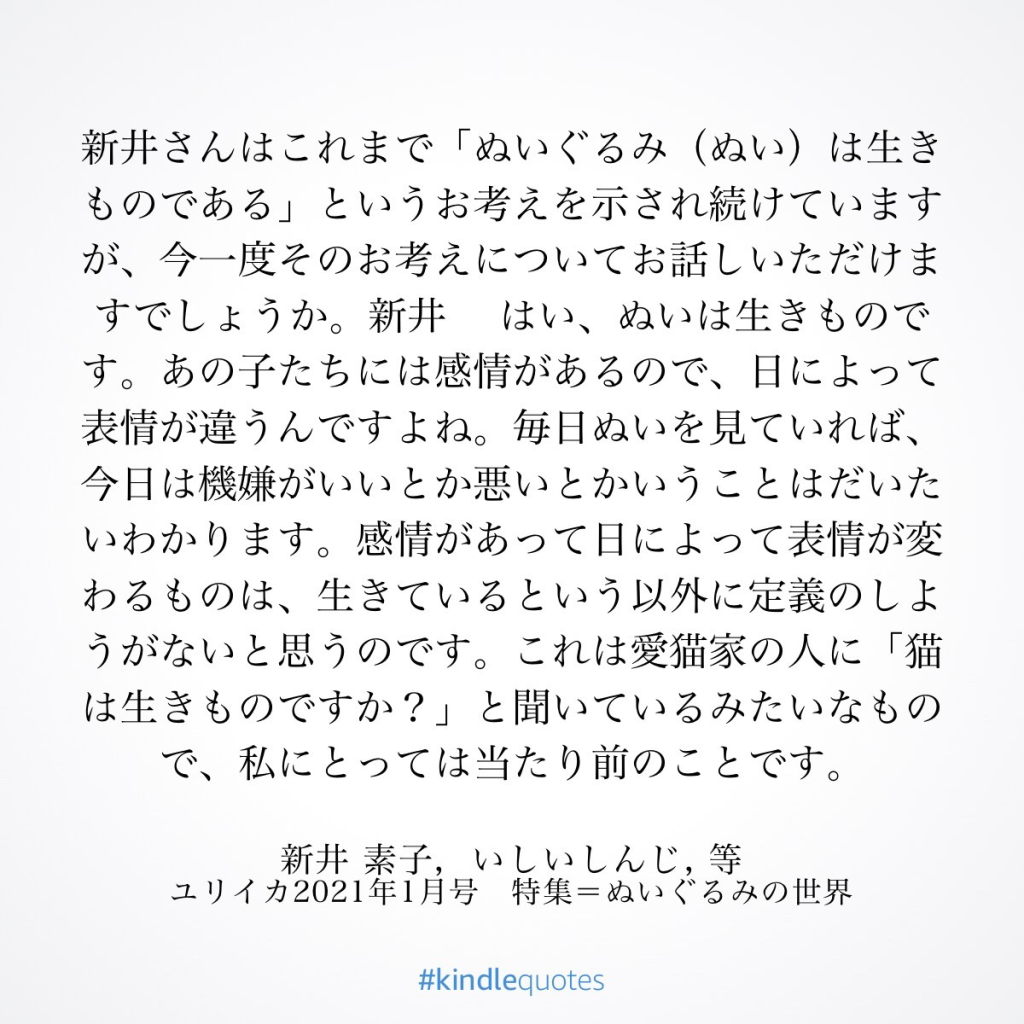激務による疲労のため、駅のホームで倒れてしまった医療機器メーカーの営業マン・永田聖。介抱してくれた駅員にお礼がしたい聖は、後日その駅員・来栖修平に再会する。お礼を伝えるも「気にしないでください」と遠慮する修平に、聖は強引に名刺を渡してごはんの約束を取り付けた。約束の日、開口一番に体調を気遣ってくれる修平の優しさに、心があたたまるのを感じる聖。同い年で気さくな修平との出会いは、仕事で私生活や交友関係をないがしろにしていた聖に変化をもたらし…。(引用:裏表紙のあらすじより)
柴田先生の『スキップしたいな』はシーモアで単話が発売されたときから追いかけていたのですが、その頃わたしは転職後で激務が続き、気が付けば寝る以外は仕事のことばかり考えていました。行動範囲は家と職場、ときどきスーパー。自分は何に心を動かされて、どんなことが好きなのか、言葉にする時間がない。そんな状況が、この作品に登場する永田くんとリンクしているような気がして、読むたびにいつも励まされていました。(作品の舞台が京都なので、その点も身近に感じたのかもしれない)
好きなシーンはたくさんありますが、私は永田くんと来栖くんが初めて一緒にご飯を食べた日の会話が印象に残っています。
「僕今日めっちゃ楽しかった ありがとう」
「あっ ……俺も!楽しかった ありがとう! 」
「うん ほなおやすみ」
何気ない会話かもしれないけれど、今日楽しかったと伝えることって意外と難しい。楽しむ気持ちを忘れていたら、もっと難しい。でもそういう壁をひょいっと軽く飛び越えてくる来栖くんがいてくれたから、永田くんは楽しさを思い出せたのかもしれない。こんな場所に金木犀が咲いているとか、電車内で永田くんが勤務する会社の広告を見つけるとか、出会った人の影響で物や景色の見方・捉え方が変わっていく様子が丁寧に描かれているのもいいなと思った。
後半では永田くんの知りたい気持ち/来栖くんの知られたくない気持ち、そして永田くんが無意識に来栖くんを傷つけてしまったことを反省するシーンがある。時間がかかったとしても、それでも対話をやめず、ちゃんと謝って好きという想いを伝えるところもすごく良かった。
柴田先生の作品はケアの描写がたくさん出てくる。それがすごくあたたかくて優しい。あと本当に絵が上手い。登場人物の表情が豊かだし、ご飯も美味しそうだし、ふきだしや背景の柄もかわいい。読んでいるとにんまり笑顔になります。基本的に漫画は電子で買うことが多いんだけど、紙でもゲットできて嬉しい。読み終わった後は思わずスキップしたくなる、そんな作品だった。